中波AM放送が将来的に終了する方向で進んでいます、多くの民放AMラジオ局は2028年秋までにFMラジオ(ワイドFM)への転換を目指しており、NHKも2026年度からAMラジオを1波に整理・削減する方針です。
深夜放送や遠距離受信を楽しんでいた者にとっては、随分と寂しいことであります。
なぜAMラジオ放送がなくなるのか
- 老朽化した送信設備の維持コスト: AM放送の送信設備は設置から50年以上経過しているものが多く、その維持・更新には莫大な費用がかかり、ラジオ局の経営を圧迫する大きな要因となっています。
- ワイドFM(FM補完放送)の普及: AMラジオの難聴対策として導入されたワイドFMは、AM番組をFM波で放送するもので、災害時の情報伝達手段としても期待されています。これにより、AMとFMの両方の設備を維持する二重のコスト負担が生じていました。
- 聴取環境の変化: 若年層を中心に、radikoなどのインターネット配信サービスやポッドキャストなど、多様な音声コンテンツの利用が増えています。スマホがあれば雑音もなくクリアーな放送を楽しむことができるようになりました。
AM放送からワイドFMに変わるとどうなるのか
- 音質の向上: FM放送はAM放送に比べて音質が良く、クリアな音声で番組を楽しむことができます。
- 災害時の強靭性: FM放送はAM放送に比べて建物による影響を受けにくく、災害時により安定した情報提供が期待されます。
- 受信環境の整備: 今後、ワイドFM対応のラジオ受信機の普及がさらに進むことが予想されます。一部のAM局では、AM放送停止に伴いワイドFM対応ラジオを配布する取り組みも行われています。
インターネット配信のさらなる活用
- radikoの普及: radikoなどのインターネット配信サービスは、地域や時間にとらわれずにラジオ番組を聴くことができるため、今後も重要な役割を果たすでしょう。
- 多様なコンテンツ提供: インターネット配信は、音声だけでなく、映像やテキストなどと組み合わせたリッチなコンテンツ提供の可能性も秘めています。

ラジオの役割はどうなっていくのか
- パーソナリティとの距離感: ラジオならではのパーソナリティとリスナーの距離の近さや、リアルタイムのコミュニケーションは引き続き魅力となるでしょう。
- ニッチなコンテンツの台頭: ターゲットを絞ったニッチな番組やコミュニティFMのような地域密着型の放送は、引き続き一定の需要があると考えられます。
- 情報源としての信頼性: 特に災害時においては、テレビやインターネットが使えない状況でも、バッテリー駆動のラジオは貴重な情報源として期待できます。
今後の課題と懸念点
- 高齢者層への影響: ワイドFM対応ラジオへの買い替えやインターネットサービスの利用に抵抗がある高齢者層への配慮が課題となります。
- 難聴地域のカバー: AM放送の広範囲なカバー能力が失われることで、山間部などの一部地域でラジオが聴きづらくなる可能性があります。
- 災害時の情報伝達体制の確保: AM放送が果たしてきた災害時の情報伝達の役割を、FM放送やインターネット配信が完全に代替できるかどうかの検証と対策が重要になってくるでしょう。
まとめ
AM放送の終了は、ラジオ放送の歴史における大きな転換点ではありますが、同時に、FM放送やインターネット配信といった新たな技術を活用し、ラジオがさらに多様な形で発展していく機会でもあります。
リスナーのニーズに応え、社会に貢献し続けるための、新しいラジオのあり方が模索されていくことになるでしょう。
夜に遠くの放送を受信する楽しみはなくなりますが、これも時代の流れで仕方がないのでしょうね・・・
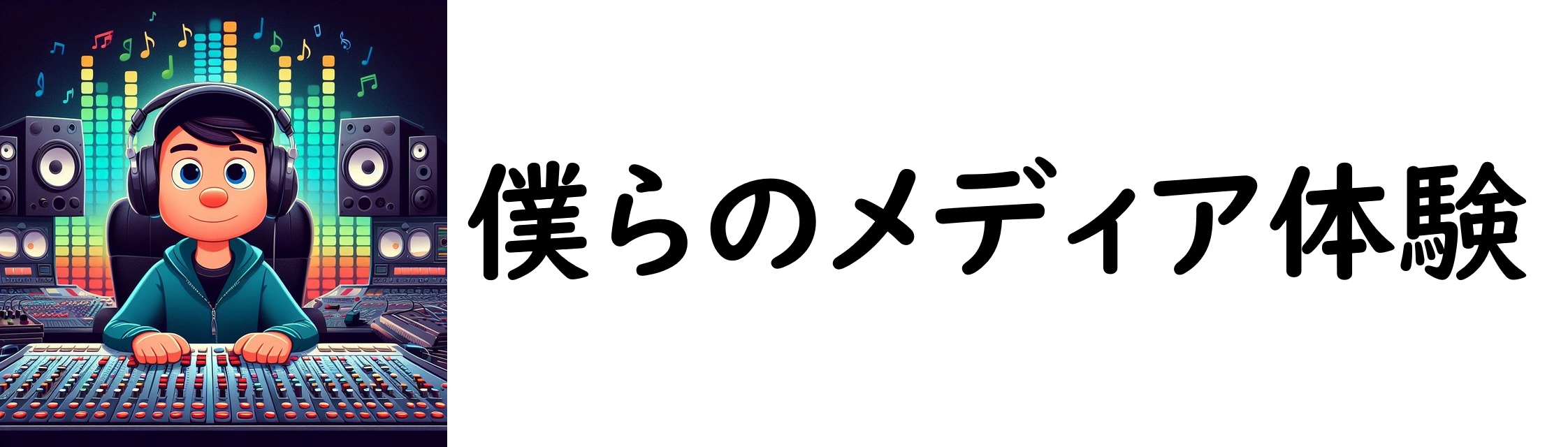
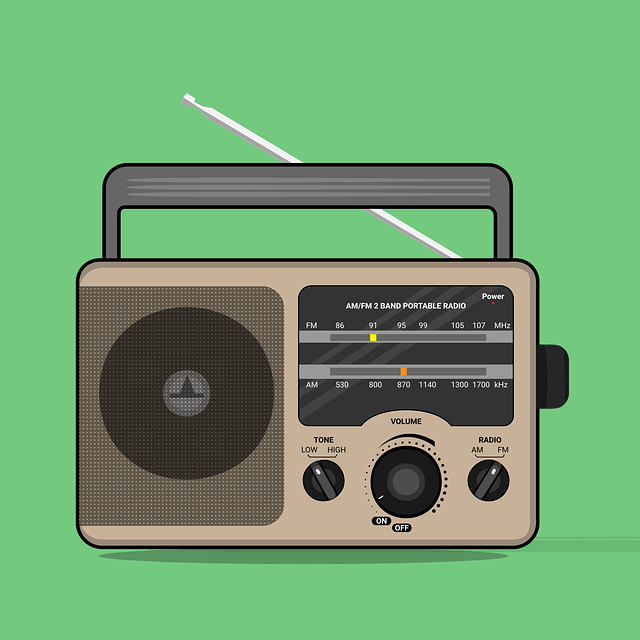

コメント